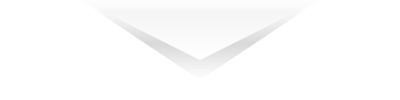マイホームをお持ちの方であれば、大半が火災保険に加入しており、近年では、賃貸住宅の入居条件として火災保険の加入を求められるケースも多くあります。
火災保険は火災による被害だけではなく、風災や水害などの自然災害も保険の対象となるため、地震の際の被害も対応できると誤解されている方も多いですが、地震が原因で発生した災害の場合は、地震保険に加入していないと補償されませんので注意が必要です。
このページでは、地震で建物が被害を受けた時に利用できる地震保険の適用条件や地震保険が使えるケース、利用するときの手順などについて説明いたします。
地震保険とは
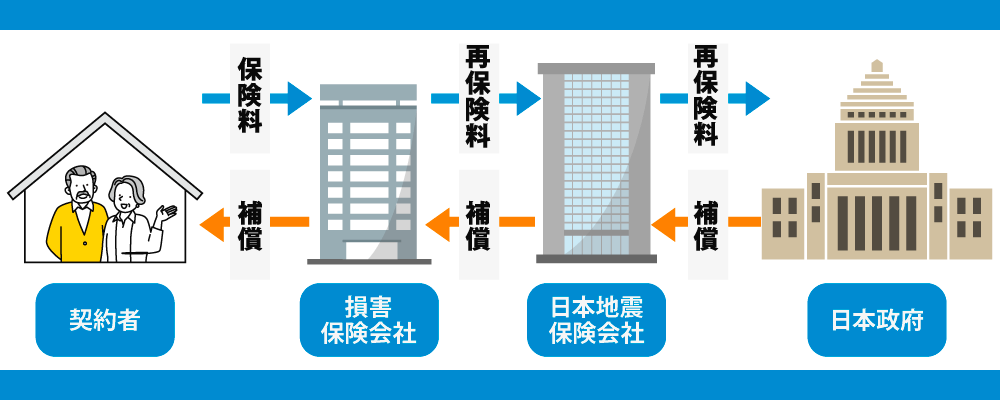
地震保険とは、火災保険では補償されない地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による損害に対応する保険のことです。単体で加入するものではなく、火災保険のオプションとして契約する必要があります。
また、地震保険は、地震保険法に基づいて国と保険会社が共同で運営している制度で、損害保険会社が支払う保険金の一部を政府が負担する再保険制度が導入されています。
政府が損害保険会社をバックアップしている公共的な制度のため、どこの保険会社で入っても、地震保険の補償内容や保険料は同じという特徴があります。
地震保険の加入率が低い理由
日本は、地震大国と呼ばれるほど、諸外国と比較しても地震の発生数が非常に多い国ですが、日本損害保険協会の2021年度の統計によると、全国の地震保険世帯加入率が約35%と、あまり加入率は高くありません。
その理由としては、以下のようなことが理由と考えられます。
火災保険で補償されると勘違いしている
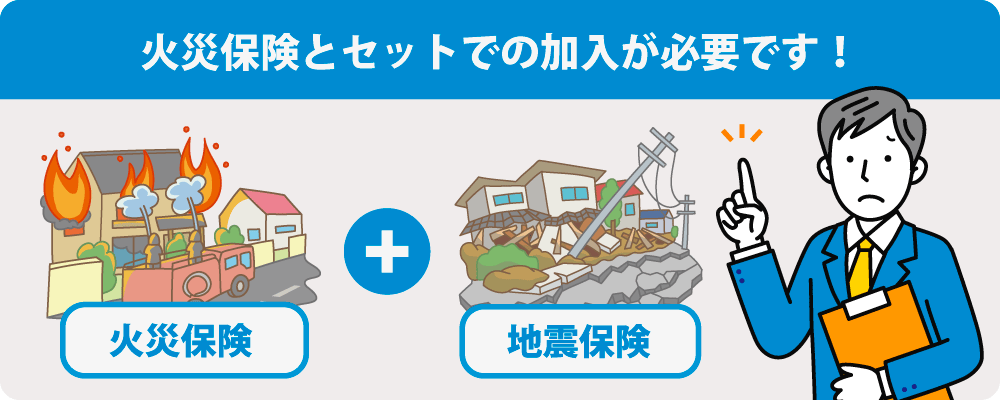
火災保険は、火災による被害だけではなく、風災や水害などの自然災害も保険の対象となるため、地震の際の被害にも対応できると誤解されている方も多いです。
地震も自然災害のひとつではありますが、火災保険では補償対象外となりますので、地震による損害の補償を受けるためには火災保険とセットで地震保険を備える必要があります。
最大で火災保険金額の半分までしか補償されない

地震によって建物や家財が全壊や全焼したとしても、最大でも半分しか補償されないという点も加入率が低い理由として考えられます。
地震保険の契約金額には、火災保険で設定した保険金額の最大50%までしか設定できないという決まりがあります。火災保険を2000万円で設定した場合を例に挙げると、地震保険で設定できる上限は1000万円までとなります。
さらに、保険金額についても上限が決まっており、建物で5000万円、家財で1000万円までと定められているため、全てが補償されるわけではありません。基本的に地震で失った建物を地震保険の補償だけで再建することはできませんので、さしあたり生活に困らないための補償と考えるのがいいでしょう。
保険料が高い
地震保険の保険料は、都道府県と建物の構造、保険金額、保険期間(契約年数)、耐震等級割引などの割引率によって決められており、どこの保険会社で契約しても保険料は変わりませんが、東日本大震災以後4回も値上げがされています。
また、保険料の地域差が非常に大きいため、地域によっては金額負担が大きくなります。2022年1月開始の保険で、保険期間1年、保険金額1000万円のケースでは、地域ごとの保険料は以下のようになっています。
| 都道府県 | 基本料率 | |
|---|---|---|
| 鉄骨・コンクリート造 | 木造 | |
| 東京都 | 27,500円 | 41,100円 |
| 埼玉県 | 26,500円 | 41,100円 |
| 神奈川県 | 27,500円 | 41,100円 |
ちなみに、地震保険の保険料に関しては、地震に強い建物であれば免震等級割引や耐震等級割引などが適用されることで、保険料が安くなるケースもあります。
地震保険料は、日本損害保険協会による地震保険特設サイトでも試算することができます。
地震保険が適用される条件
地震保険が適用される条件は、以下の通りです。
地震保険の対象
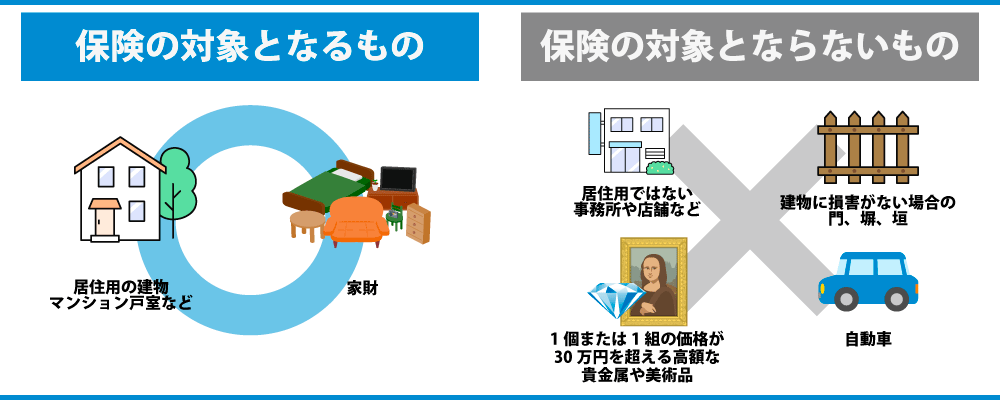
地震保険の補償対象となるのは、「建物」「家財」の2つです。保険の契約時に、「建物のみ」「家財のみ」「建物と家財」の3つのうち、いずれかひとつを選ぶことができます。
また、建物の場合は、居住用に使用される建物であれば、マンションや店舗併用住宅であっても適用されます。ただし、居住用の建物ではない事務所や店舗などは地震保険の対象外となるので注意が必要です。また、建物に損害がなかった場合の門、塀、垣の損害についても対象外となります。
家財の具体例
家財とみなされるものとしては、食器類・電気器具類・家具類・身の回りの品・衣類寝具類の5種類が該当します。それぞれの具体例は以下の通りです。
| 食器陶器類 | 食器・調理器具・陶器置物・食料品 |
|---|---|
| 電気器具類 | 冷蔵庫・洗濯機・テレビ・パソコン・電子レンジ・掃除機 |
| 家具類 | 机・イス・食器棚・タンス |
| 身の回りの品 | 書籍・靴・かばん・カメラ・レジャー用品 |
| 衣類寝具類 | 衣類・ベッド・布団 |
ただし、自動車や1個または1組の価格が30万円を超える高額な貴金属や美術品、動物や植物、通貨などは補償の対象外となります。
地震保険の対象となる被害
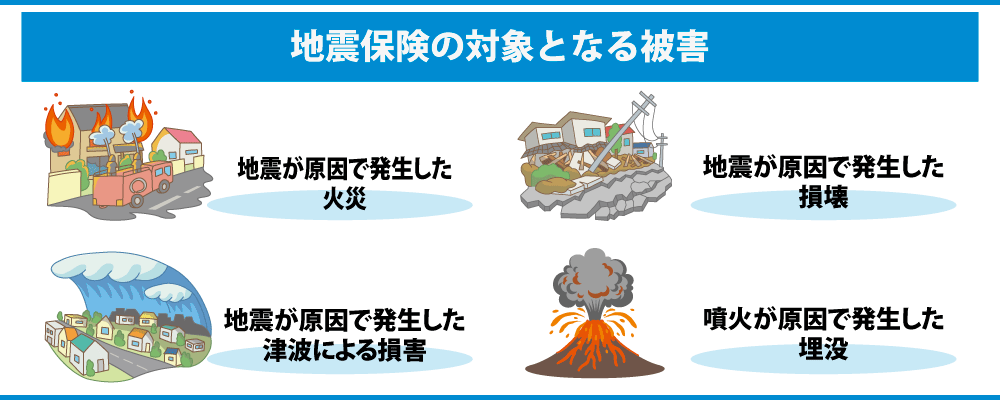
地震保険の対象となる被害としては、以下のような被害が該当します。
・地震が原因で発生した火災
・地震が原因で発生した損壊
・地震が原因で発生した津波による損害
・噴火が原因で発生した埋没
例えば、「地震によって転倒したストーブによる火災」や「地震によって瓦がズレたり落ちてしまった」といった場合は、地震保険で補償される可能性があります。
地震発生翌日から10日以内に生じた損害

基本的に、地震発生の翌日から10日以内に生じた損害のみが補償の対象となります。期間が設けられている理由としては、、日数が開いてしまうと地震が原因の損害なのかを判断するのが難しくなるからです。
ただし、すぐに損害に気づけない場合もあるため、地震などが発生してから10日を過ぎたとしても、鑑定士に「地震による損害」と判断されれば補償の対象となりますので、保険法で定めらた保険の請求期限である3年までに手続きを行う必要があります。
また、3年という期間はあくまでも保険法に基づいた期限であり、加入している保険会社によっては、それよりも短い請求期限となっている可能性もあります。
反対に、保険会社や災害の規模によっては、3年以上前の損害でも補償が受けられる特例措置が設けられている場合もありますので、ご自分が加入している地震保険の約款を確認したり、保険会社へ直接請求期限を問い合わせてみるのも良いでしょう。
地震保険で受け取れる金額
地震保険での保険金支払額は、被害状況によって決まります。損害の程度は、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階に分けられ、もし一部損に至らない場合は、保険金を受け取ることはできません。
建物の場合
建物における損害の程度と、保険支払額の割合です。建物に対する補償の限度は、同一敷地内ごとに5000万円となります。
また、支払額は建物の時価によっても大きく変わります。たとえ全損の評価であったとしても、建物の年数が経過して時価が下がっている場合は、契約した保険金全額もらえなくなる可能性があるので注意が必要です。
| 損害の程度 | 定義 | 受け取れる金額 |
|---|---|---|
| 全損 | 以下のいずれか ・建物の主要構造部の損害額が、建物の時価の50%以上 ・焼失または流失した床面積が、建物の延床面積の70%以上 |
保険金額の100% (時価が限度) |
| 大半損 | 以下のいずれか ・建物の主要構造部の損害額が、建物の時価の40%以上50%未満 ・焼失または流失した床面積が、建物の延床面積の50%以上70%未満 |
保険金額の60% (時価の60%が限度) |
| 小半損 | 以下のいずれか ・建物の主要構造部の損害額が、建物の時価の20%以上40%未満 ・焼失または流失した床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満 |
保険金額の30% (時価の30%が限度) |
| 一部損 | 以下のいずれか ・建物の主要構造部の損害額が、建物の時価の3%以上20%未満 ・全損・大半損・小半損に至らない建物が、床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受けた場合 |
保険金額の5% (時価の5%が限度) |
※建物の主要構造部とは、軸組、基礎、壁、屋根等の建物の構造上、非常に重要な役割を担う部分のことを指します。
家財の場合
家財における損害の程度と、保険金額の割合です。家財に対する補償の限度は、同一敷地内ごとに1000万円となります。また、家財についても支払額はその時の時価によって変わります。
| 損害の程度 | 定義 | 受け取れる金額 |
|---|---|---|
| 全損 | 家財の損害額が、家財全体の時価の80%以上 | 保険金額の100% (時価が限度) |
| 大半損 | 家財の損害額が、家財全体の時価の60%以上80%未満 | 保険金額の60% (時価の60%が限度) |
| 小半損 | 家財の損害額が、家財全体の時価の30%以上60%未満 | 保険金額の30% (時価の30%が限度) |
| 一部損 | 家財の損害額が、家財全体の時価の10%以上30%未満 | 保険金額の5% (時価の5%が限度) |
地震保険を申請する時の流れ

地震保険を申請する際の手続きの流れは以下の通りです。
1.必要な物を用意しておく
まずは、申請に必要な書類を用意しましょう。保険証券や建物の図面などを用意しておくと手続きがスムーズに進められます。また、被害状況の写真は必ず撮影しておきましょう。
保険金の支払い金額は、被害状況などを鑑定人が調査し決定します。しかし、大規模な地震の場合、地震発生後の鑑定人が調査に来るまでかなりの時間がかかる場合があります。
その際、鑑定人が調査に来るまで倒れたものなどをそのままにしておくことはできませんので、安全が確認できたら、片づける前に必ず写真や動画に被害状況が確認できるよう写真や動画に残しておきましょう。
写真を撮影する際には、「被害箇所をアップで様々な角度から撮影した写真」と「被害箇所全体が分かるように少し遠くから撮影した写真」の2種類を撮影しておくといいでしょう。
2.保険会社に連絡する
必要書類の準備が出来たら、加入している保険会社に連絡をし、被害の報告をしましょう。一般的には加入している保険証券を確認しながら、以下の事項を保険会社へ報告します。
・契約者名
・保険証券番号
・被害の日時場所
・被害の状況・程度
・他に契約している保険
・連絡先
また、災害で保険証券を紛失してしまった場合でも、契約者本人であることを確認できれば、保険金を請求が可能です。
万が一、加入中の保険会社もわからなくなった場合でも、お住まいの地域が「災害救助法の適用された地域」または「金融庁国民保護計画に基づく対応要請のあった地域」であれば、生命保険協会または損害保険協会に問合せをすることでご自分がどこの保険会社の保険に入っていたか契約内容を確認することができます。
3.損害保険登録鑑定人による現地調査
保険会社へ被害状況の連絡をした後は、日程調整をして、「損害保険登録鑑定人」というプロの調査員が訪問し現地調査が行われます。鑑定人が訪問する際には、以下のものを準備しておくとスムーズに進めることができます。
・印鑑と振込先の通帳
・平面図(コピーを用意しておくとより良い)
・被害部分のチェック(チョークなどで印をすると良い)
この現地調査で、おおよその支払い保険金額が算出されることが多く、鑑定人から請求に必要な書類は渡されますので、内容に納得できれば必要事項を記入してそのまま提出することも可能です。
4.保険金の支払い
現地調査を終えて審査が通れば、一般的に「請求完了日から30日以内」に保険金が支払われます。保険金を受け取った後は、工事を開始します。
地震保険を申請する際のポイント
地震保険を申請する際のポイントは以下の通りです。
片付ける前に被害写真を撮っておく
 片付けや修理を行う場合は、可能な限り被害箇所の詳細な写真や動画を撮影しておくことが大切です。
片付けや修理を行う場合は、可能な限り被害箇所の詳細な写真や動画を撮影しておくことが大切です。
鑑定人も状況を把握しやすくなりますので、「食器が割れただけ」などと考えずに、念のためスマホやデジカメで記録を残すようにしてください。
余震も一つの地震として数えることがある
 地震は1回で終わりではなく、さらに余震が起こる可能性も十分にあります。地震後の余震については、最初の地震発生日から3日(72時間)経過しているかが重要なポイントになります。
地震は1回で終わりではなく、さらに余震が起こる可能性も十分にあります。地震後の余震については、最初の地震発生日から3日(72時間)経過しているかが重要なポイントになります。
例えば、「最初の地震で一部損となり、”3日以内”に余震が起こり全損となった」場合は、地震の回数は1回とカウントされますので、全損として保険金が支払われます。
しかし、「最初の地震で一部損となり、”4日後”に余震が起こり全損となった」場合は、1回目と2回目の地震が3日以上あいているため、別の地震として扱われます。その場合、1回目は一部損、2回目は全損としてそれぞれ保険金が支払われることになります。
早めに保険会社に連絡する
 基本的に保険請求書期限は3年と定められていますが、絡が遅くなってしまうと、地震によって生じた被害なのか、経年劣化によって生じたものなのかが判断しづらくなり、審査が厳しくなってしまう可能性があります。
基本的に保険請求書期限は3年と定められていますが、絡が遅くなってしまうと、地震によって生じた被害なのか、経年劣化によって生じたものなのかが判断しづらくなり、審査が厳しくなってしまう可能性があります。
そのため、被害を発見したら速やかに保険会社に連絡することが重要です。
支払われた保険金に不満がある場合は相談する
 災害規模が大きいほど多くの人が申請します。そのため、鑑定人も慌ただしくなり、被害の見落としが起こる可能性も無いとは言いきれません。
災害規模が大きいほど多くの人が申請します。そのため、鑑定人も慌ただしくなり、被害の見落としが起こる可能性も無いとは言いきれません。
もし、判定に不服がある場合には再度被害状況を見てもらえないか交渉してみてください。その後の再調査でもさらに不満があるという場合は、日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」に相談してみましょう。
そんぽADRセンターは、門の相談員が損害保険に関する相談に乗ってくれる専門の窓口で、保険会社とのトラブルに関する苦情受付や和解案の提示など問題解決に向けての支援などを行っています。
まとめ
地震保険とは、火災保険では補償されない地震・噴火・津波を原因とする損害に対応する費用の一部を補償してくれる制度です。単体で加入するものではなく、火災保険のオプションとして加入する必要があります。
また、地震保険は被害状況を実際に鑑定人が訪問して調査するため、災害規模が大きいほど多くの人が申請すると日程調整に手間がかかり、時間もかかりますので、保険金も支払いが遅くなる傾向にあります。
そのため、被災後落ち着いたらすぐに保険会社へ連絡することが大切です。
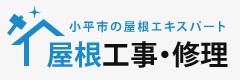
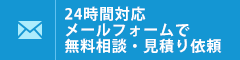
 お気軽に
お気軽に 満足度96.0%!
満足度96.0%!